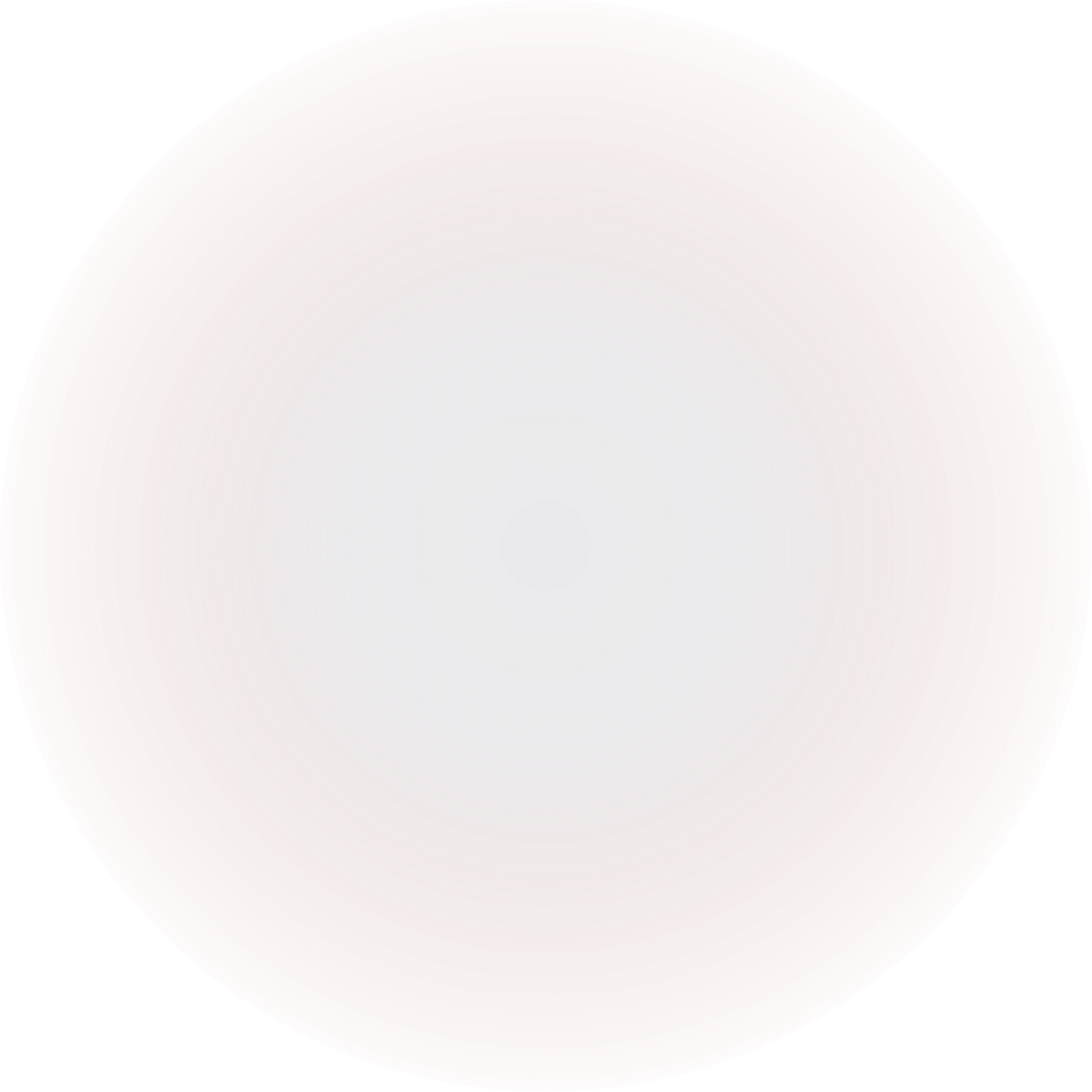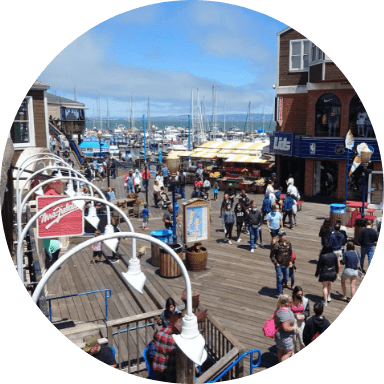留学を希望した理由
私は入所当時から、特定の分野のプロフェッショナルになることよりも、依頼者のいかなる法律相談にも広く対応できるようなジェネラリストを目指して弁護士としての業務を続けてきました。そのため、紛争解決においては、会社法関係訴訟を中心としつつ、一般民事訴訟、労働訴訟、知財訴訟、証券訴訟、IT関連訴訟、不動産関連訴訟、企業不正関連訴訟等、幅広く経験を積み、コーポレート分野においても、コーポレートガバナンスをはじめとして、株主総会、株主アクティビズム対応、役員報酬関連の相談等、多くの相談を受けてきました。入所してしばらくの間は、これらの業務の大半が国内の事案でしたが、年次が上がるにつれ、海外の依頼者の訴訟対応や、英語の会議での法律相談、英語のドキュメントのレビュー等の業務が徐々に増え、英語を学ぶことで、更に自身の業務の幅を広げることができると身に沁みて感じるようになりました。
また、会社法に限らないことではありますが、アメリカの実務は日本の数年先をいっていることが多く、アメリカの実務を参考に日本の法改正がされることもしばしばあります。実際に私が担当した会社法関係訴訟において支配株主の義務が争点となっていたことがあり、このトピックは日本では未だ法整備が進んでいない部分ではありました。他方、アメリカにおいては、Fiduciary Duties of Controlling Shareholdersという形で、これまでに既にいくつものCaseが積み重なり、一定の法解釈が存在します。このように、アメリカにおける法実務を学び、今後の日本における業務のヒントにすることで、更に自身のリーガルサービスに深みを持たせることができると考えました。特にペンシルベニア大学ロースクールは、会社法分野において非常に有名なロースクールであり、アメリカの著名な教授が多く在籍することから、ペンシルベニア大学ロースクールへの留学を希望するようになりました。
さらに、ペンシルベニア大学には、世界で最も有名なビジネススクールであるウォートンスクールがあることから、ペンシルベニア大学ロースクールの学生は、ウォートンスクールの授業を履修することや、Wharton Business and Law Certificateというウォートンスクールがロースクールの生徒向けに提供するプログラムを受けることもできます。事務所の業務においては、法的観点で事案を紐解くことももちろん重要ではあるものの、ビジネスの観点で経営陣がその瞬間に何を考えているのかを察することも重要であり、そのようなビジネススキルを学ぶためにも、ペンシルベニア大学ロースクールへの留学を希望しました。